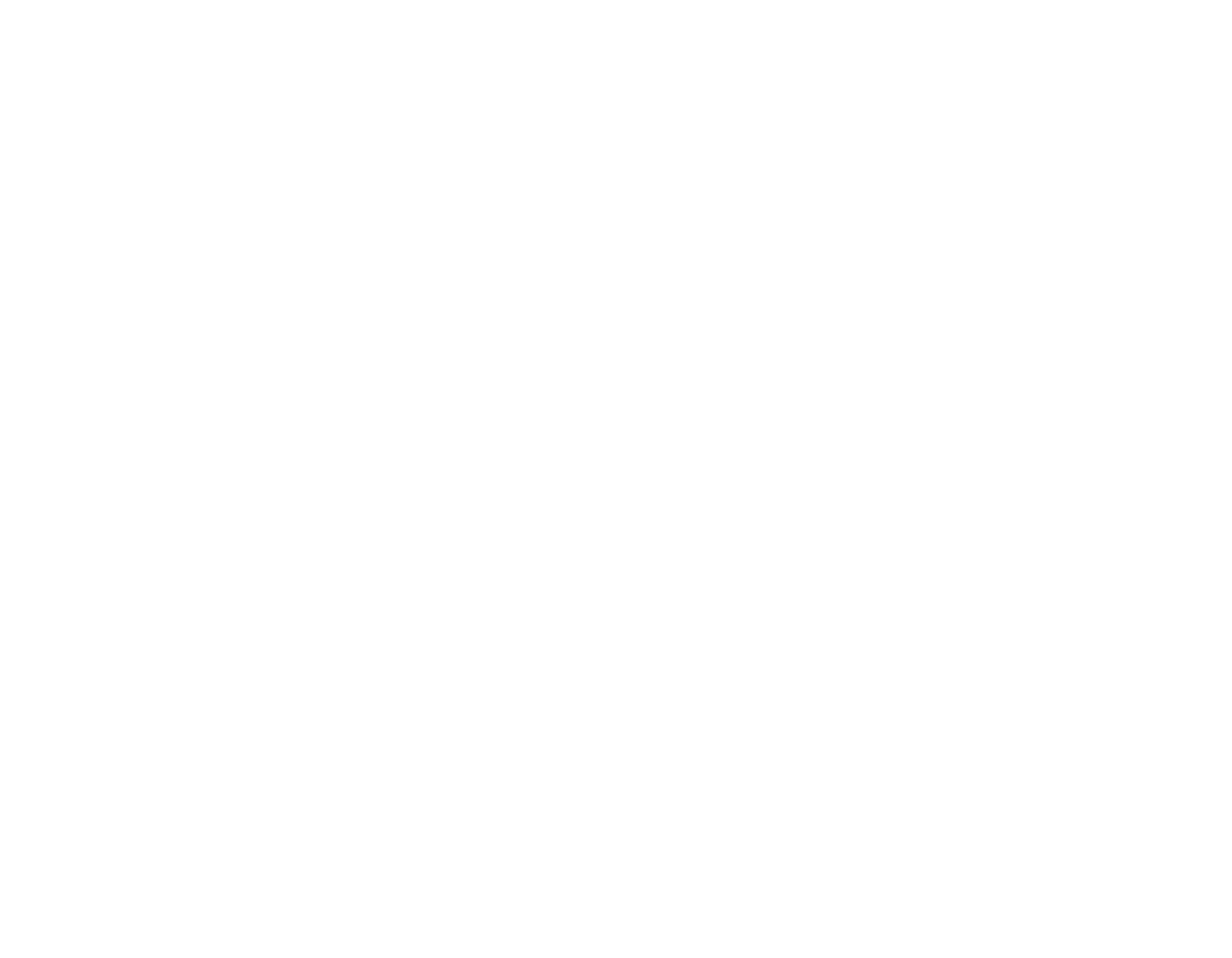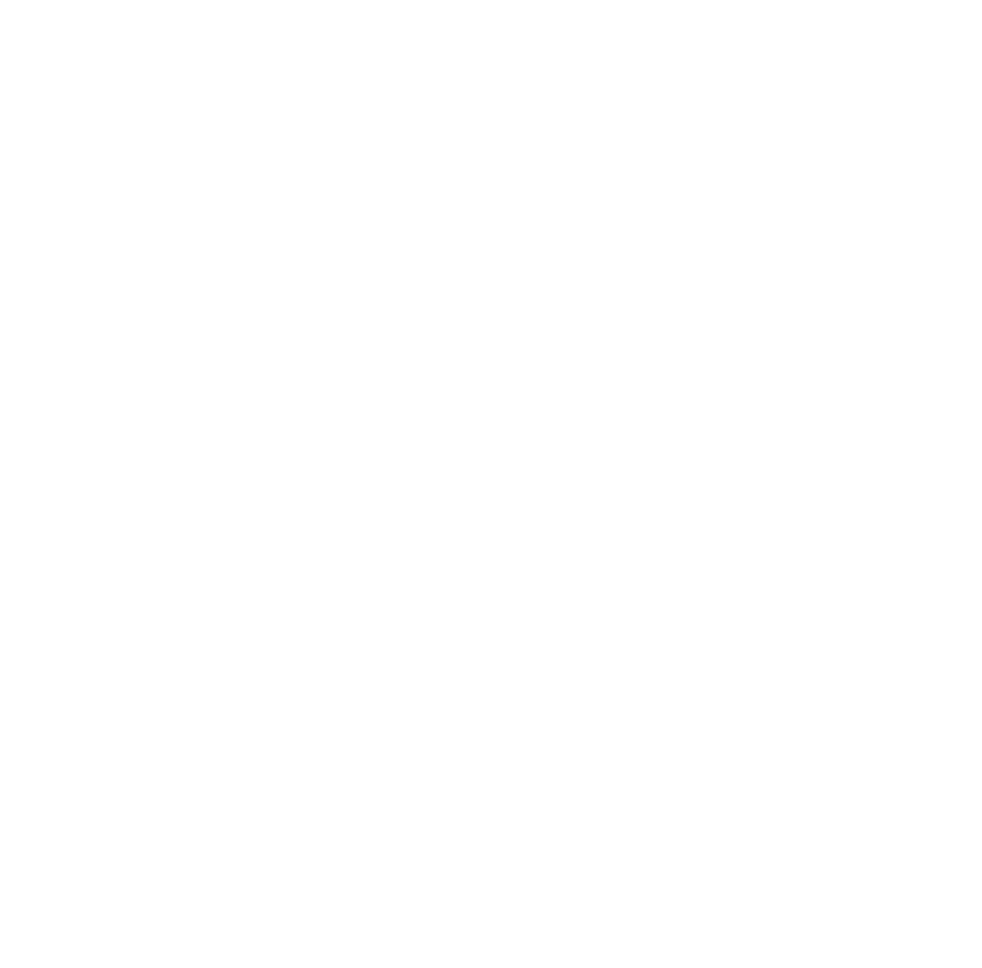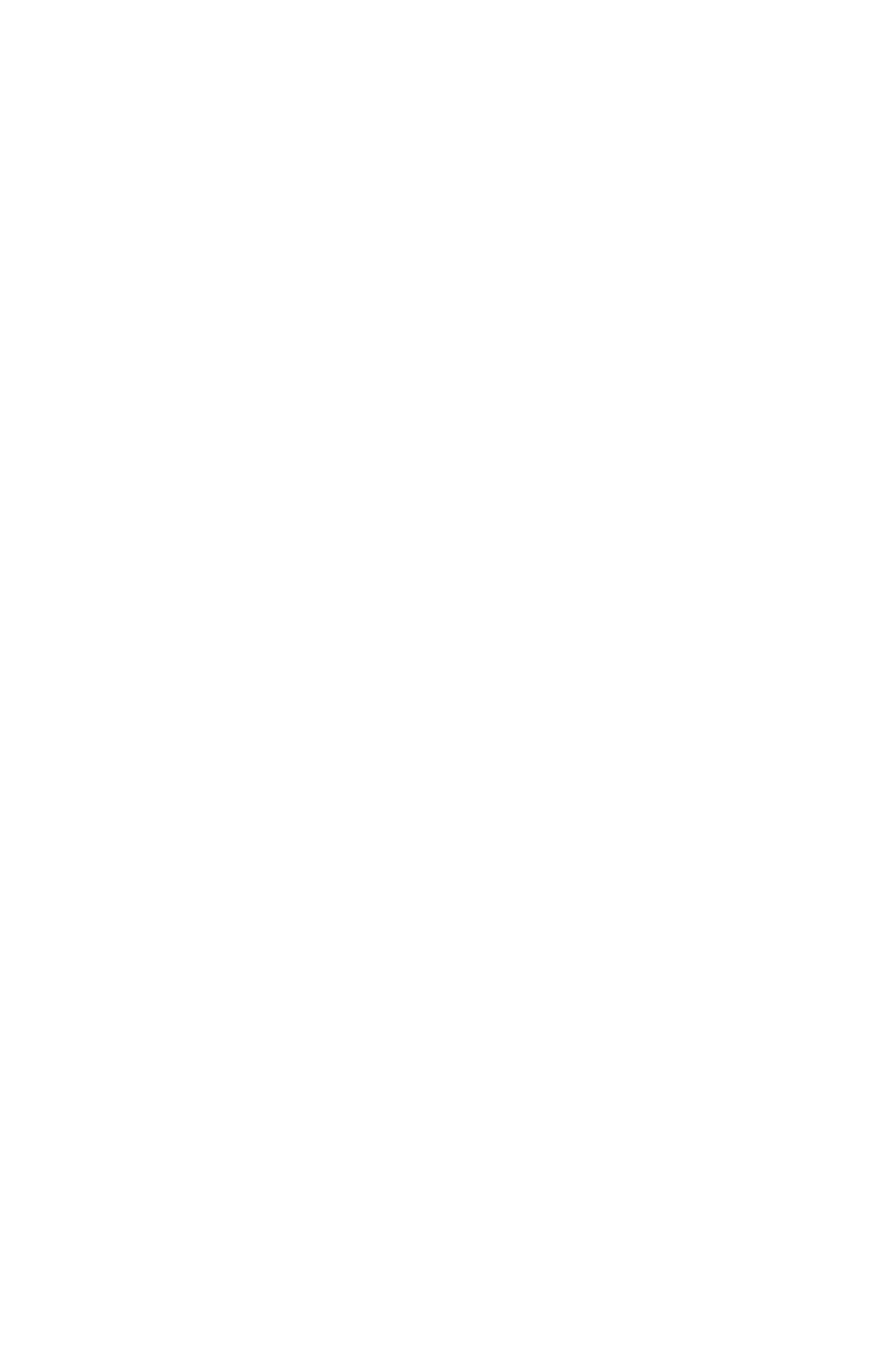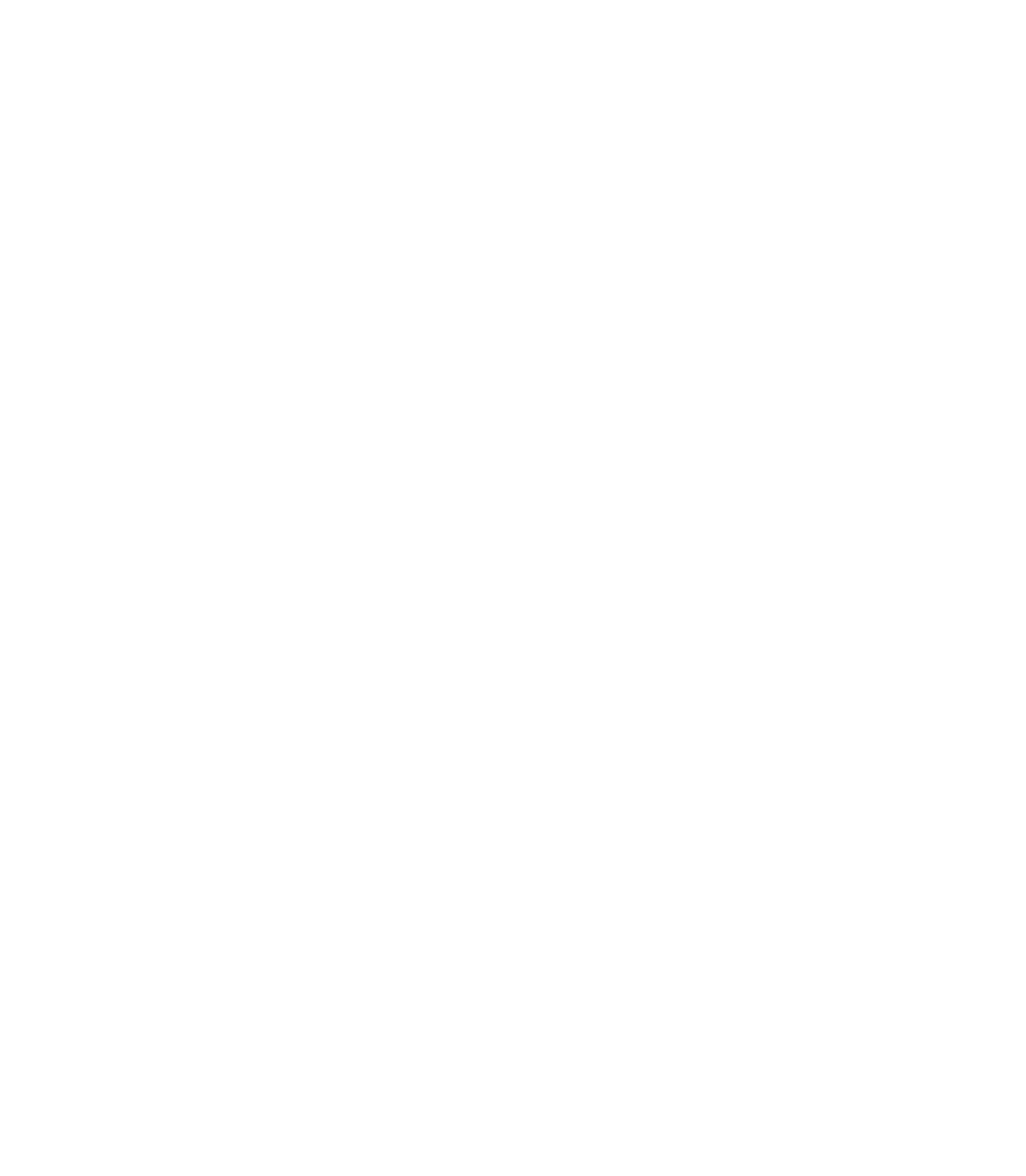ロングインタビュー
ロシア料理店スンガリー、
ロシア音楽とコロナ禍における
活動などについてお話を聞く
「77歳になり、人生がますます面白くなってきたんです」と笑顔で語る加藤登紀子さんは、コロナ禍の中でも創作を続け、周囲の人々にエネルギーを与え続けている。ロシアの歌「百万本のバラ」を歌って広く知られるようになった加藤さんは、これまで露日友好のためにたくさんのことを行ってきた。最近、2021年のロシア文化フェスティヴァルが開幕したのを受け、「スプートニク」は加藤さんにインタビューをお願いした。加藤さんにとってとても大切なロシア料理店スンガリーについて、ロシア音楽と日本音楽の驚くべき共通性について、またコロナ禍におけるコンサート活動やその他の活動などについてお話を伺った。
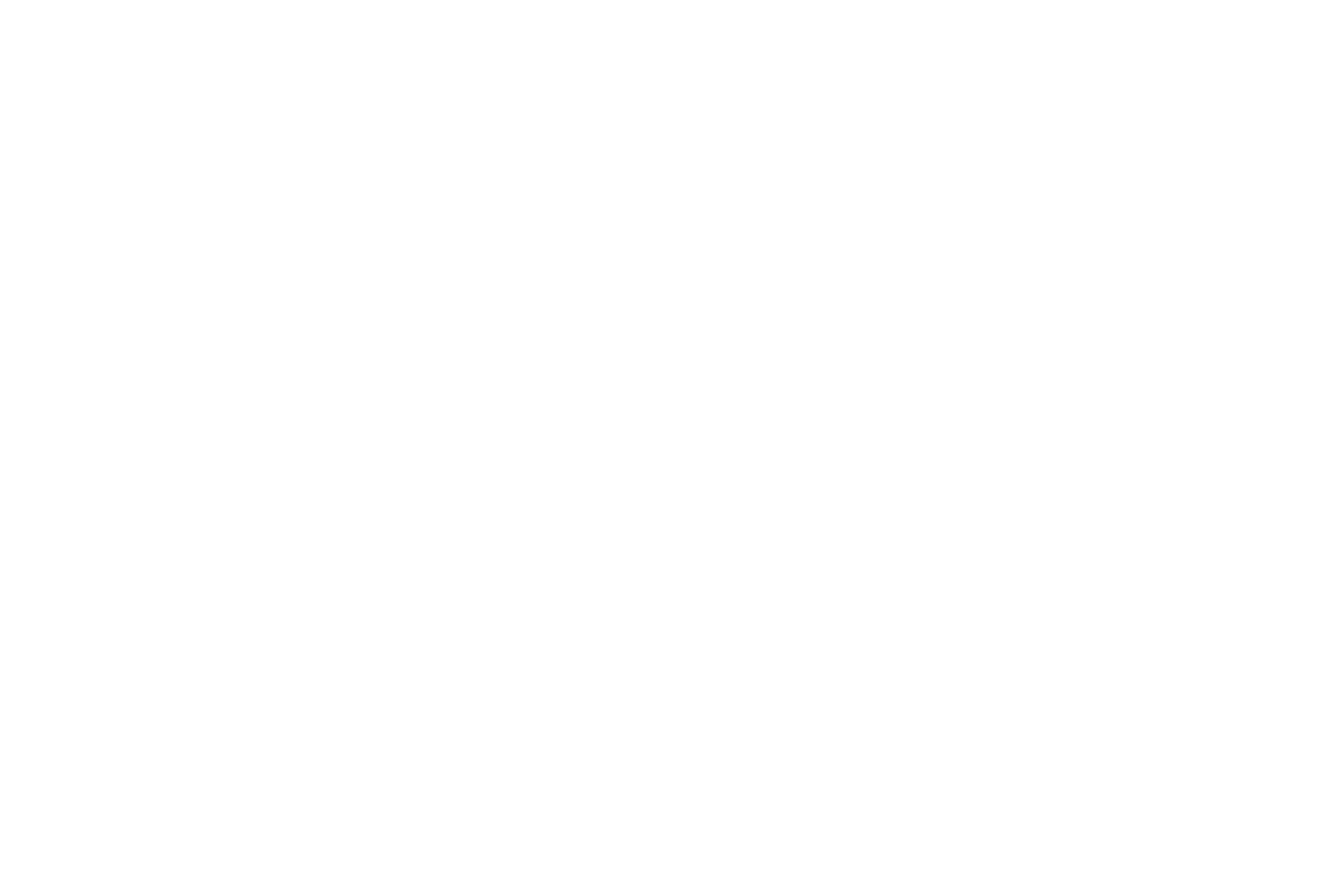
| © Sputnik/Jenny Hollyway |
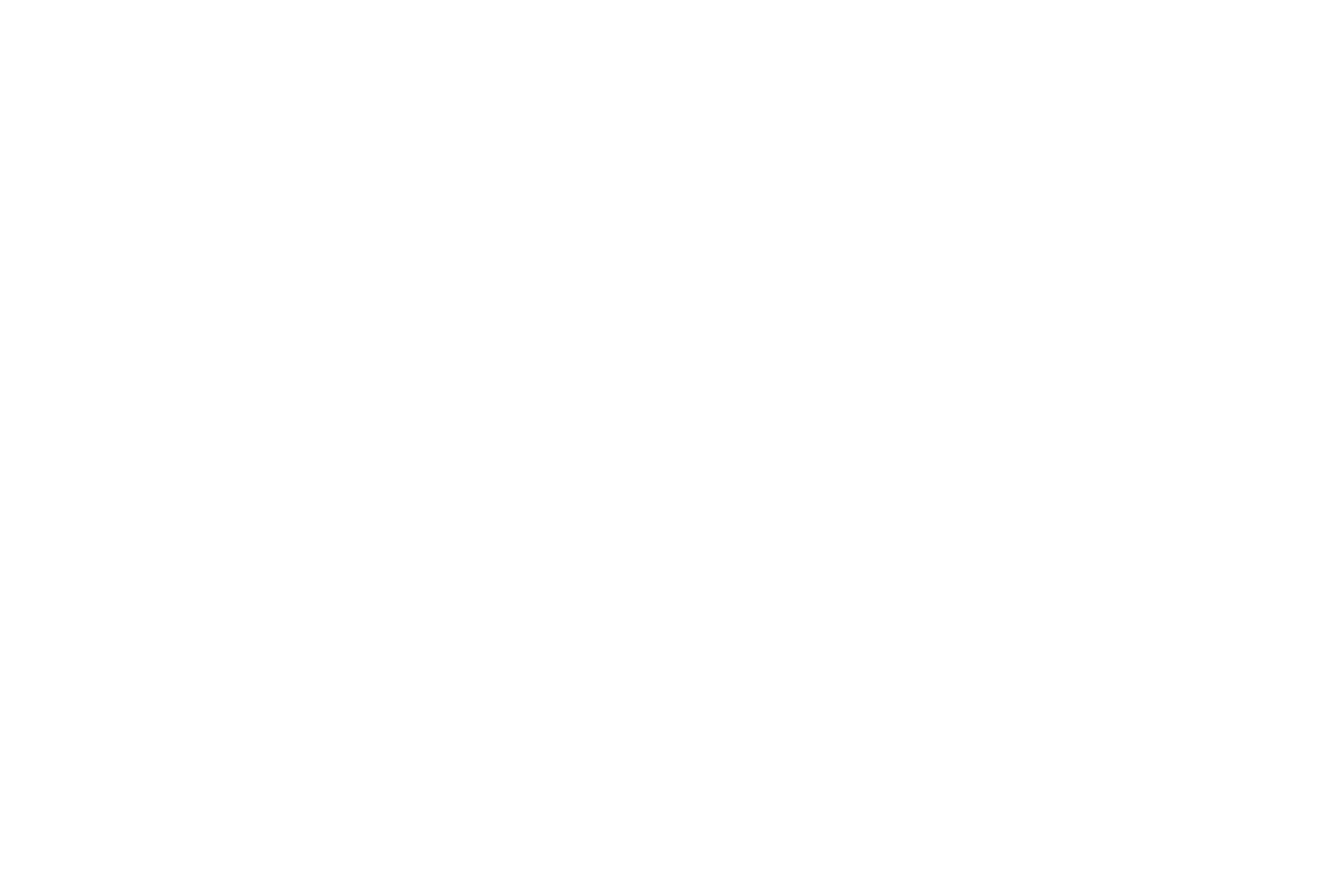
もともとレストランは1957年に新橋でオープンしたが、その後、京橋に移転し、1960年に現在の新宿に移った。しかし、このレストランの歴史はさらにその昔に遡る。
現在、レストランは加藤さんの姪の暁子さんが経営しており、東京にいくつもの店舗を構えている。現在のスンガリーの外観は、オープンしたときの姿とは違っているが、加藤さんは、お店の雰囲気は彼女が大学生だった頃のままだと語っている。
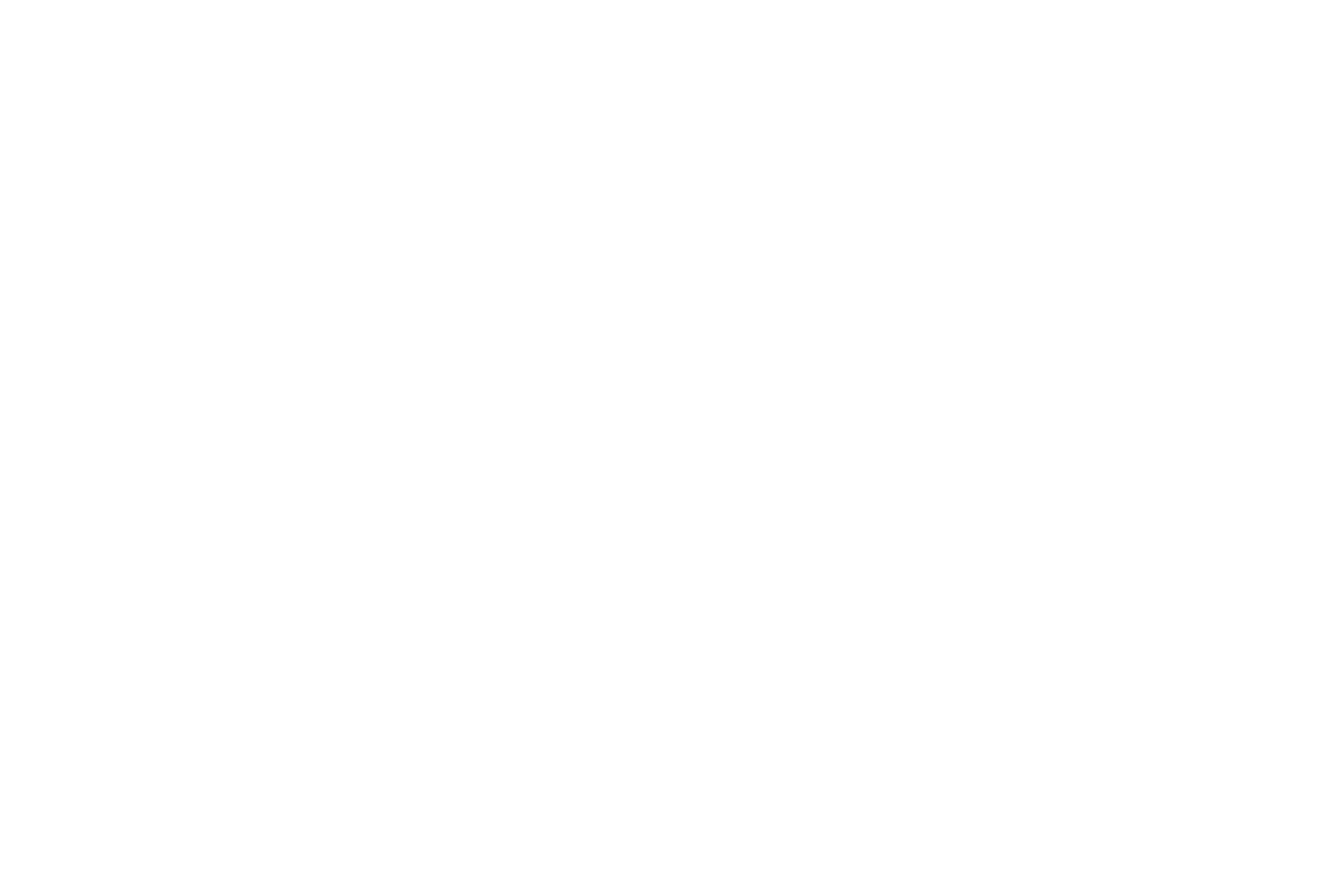
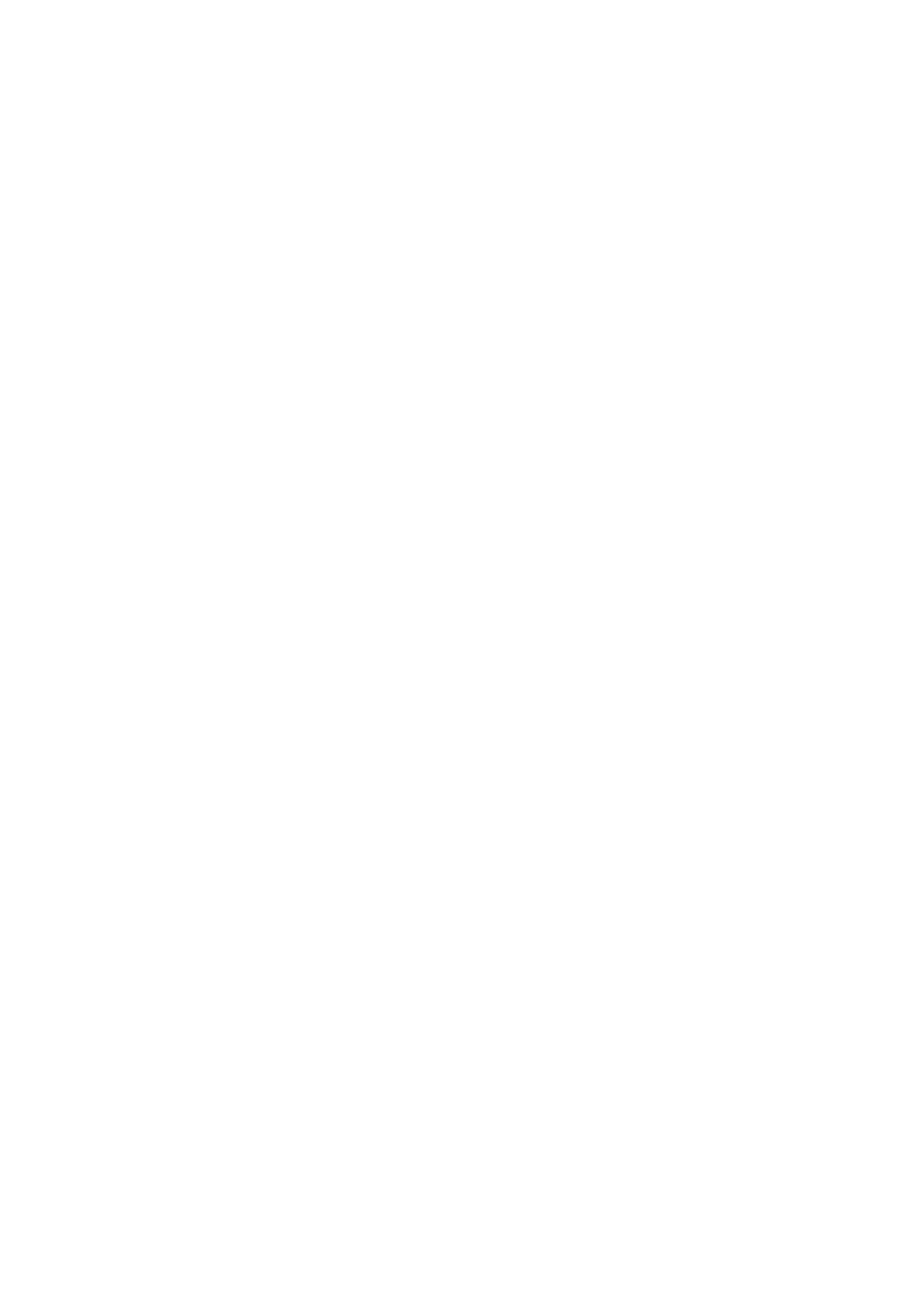 | 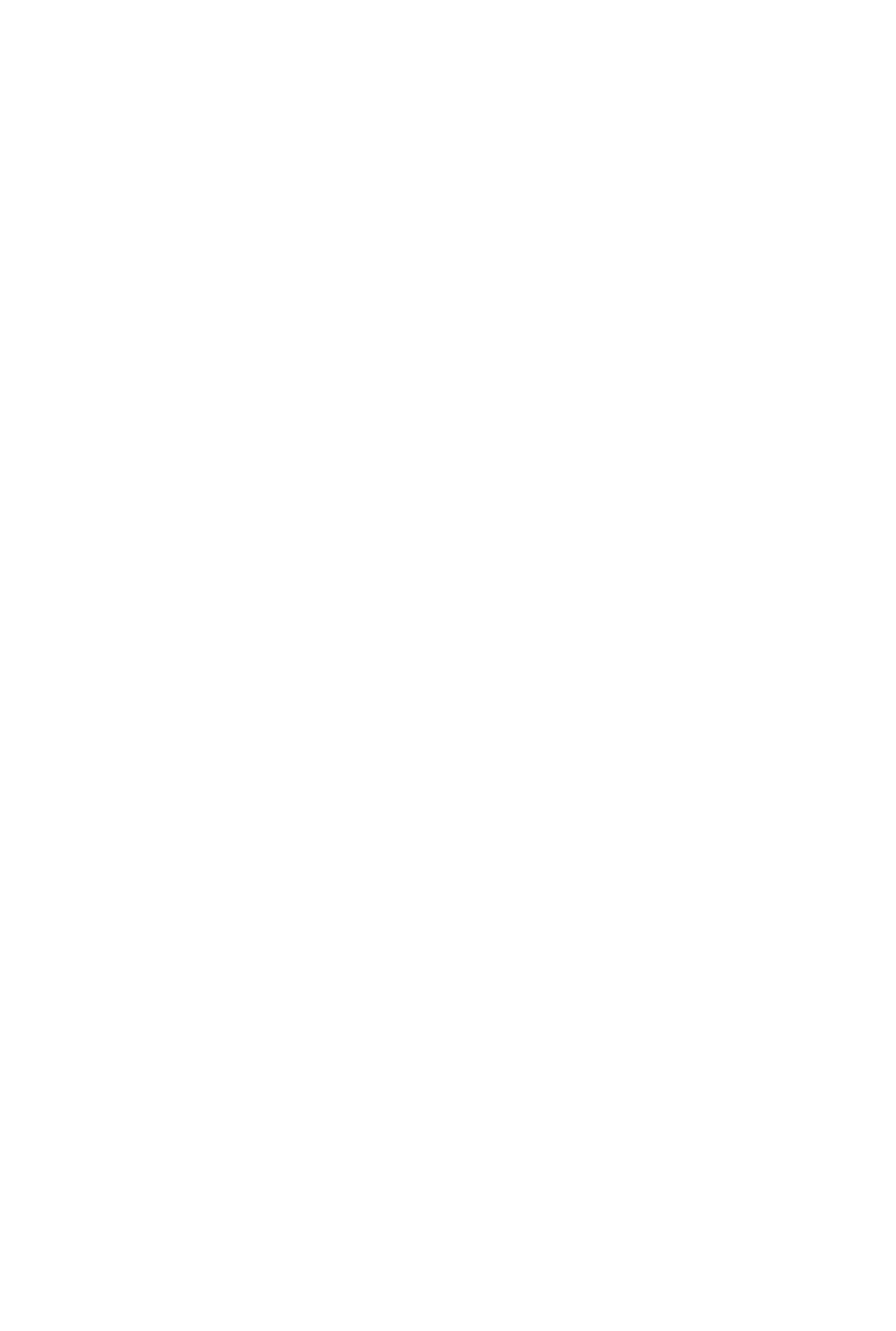 | 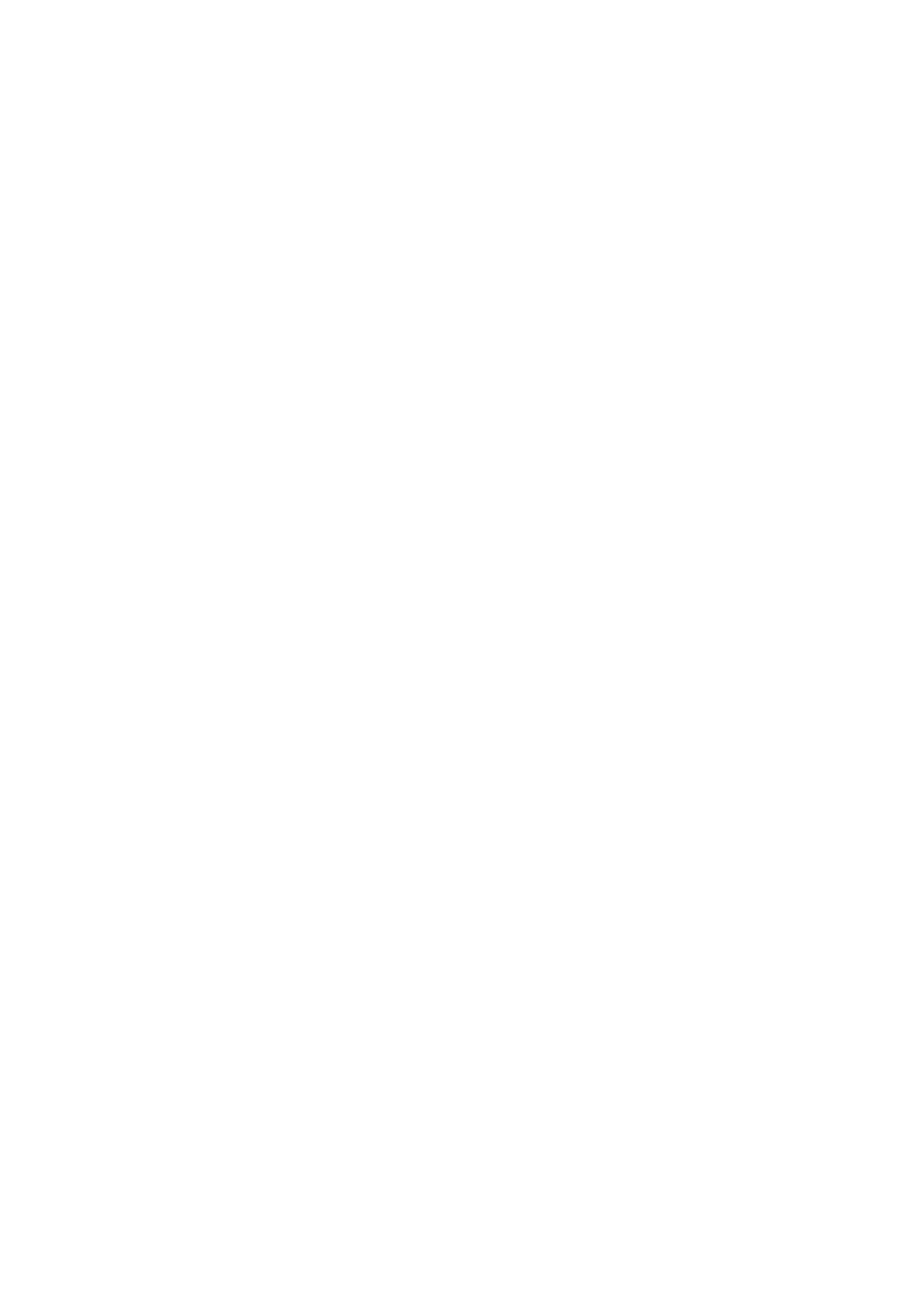 |
加藤さんは、ロシアとの友好親善は、加藤さんの父親にとってとても大切な人生の事業だったと話す。
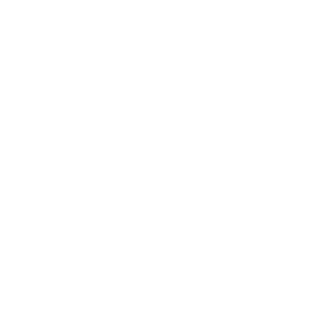
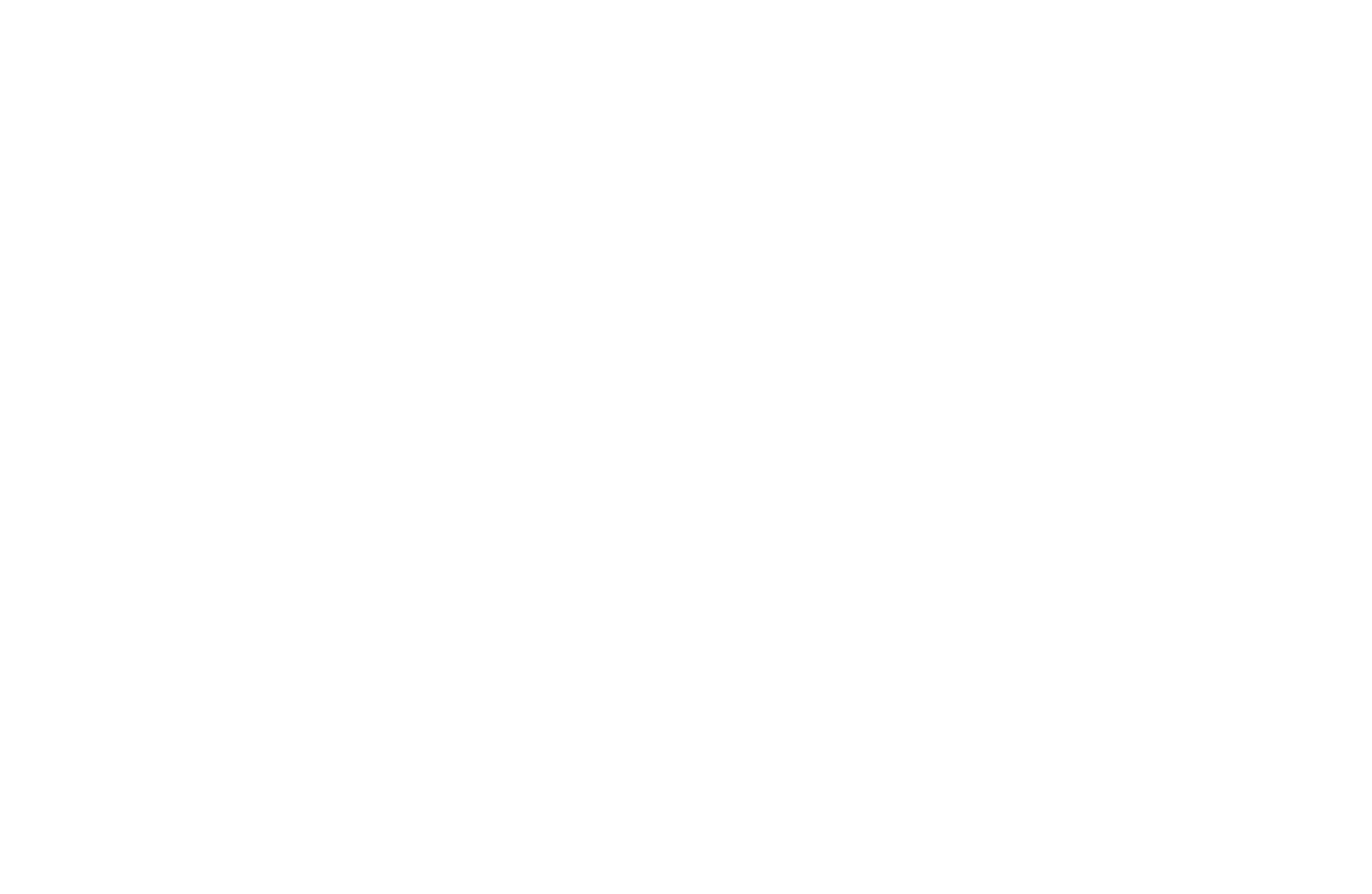
さらに加藤さんは、中でも、歌舞伎をロシアで広めたことは、父親のもっとも大きな功績の一つだと考えている。
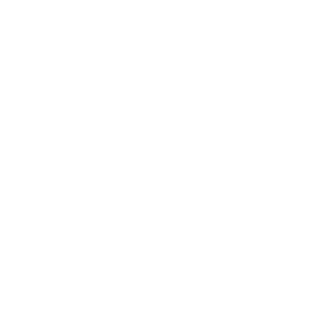
こうして加藤さんは、まだ「百万本のバラ」が世に出る前から、ソ連中を周るようになった。そして、「百万本のバラ」が1982年に書かれたとき、加藤さんはこの歌が大好きになり、自分で日本語でも歌うようになった。
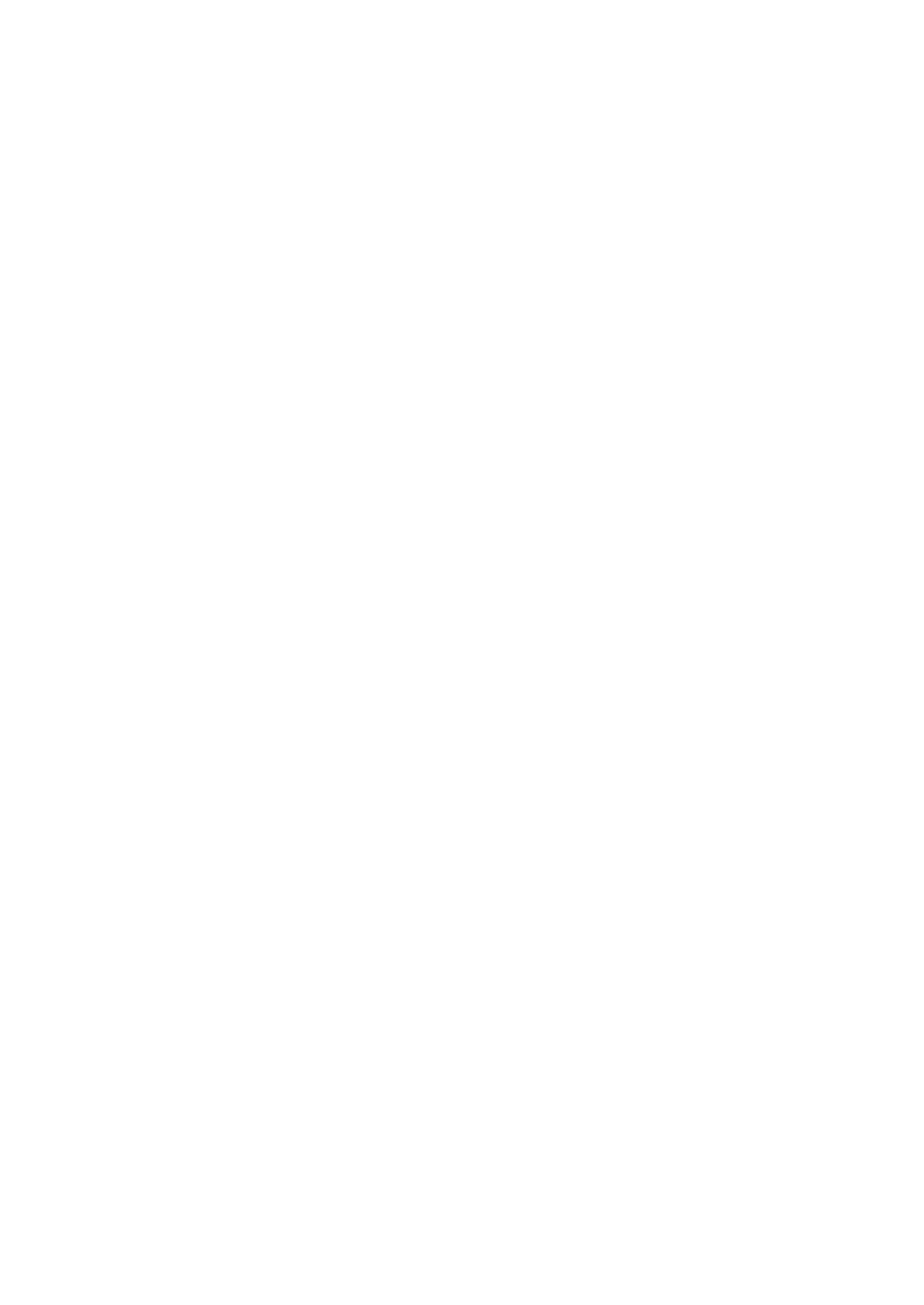
1986年にチェルノブイリ原発事故が発生したとき、加藤さんは父親とともにキエフに行き、苦しむ人々を助けたいと思っていたが夢は叶わなかった。加藤さんは、今でも、この夢を実現できなかったことを残念に思っているという。
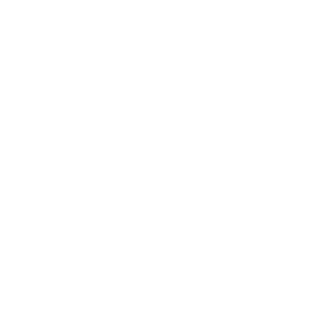
「百万本のバラ」は、ロシアの曲が日本でヒットした、あるいは逆に日本の歌が実はロシアの大ヒット曲になったという唯一の例ではありません。しかも、日本人の中には、「百万本のバラ」はもともと日本の歌だと思っている人はたくさんいますし、ロシア人の中には、たとえばロシア語版の「恋のバカンス」はもともとロシアの曲だと思っている人もたくさんいます。日本の音楽とロシアの音楽はなぜ似ていると思われますか?
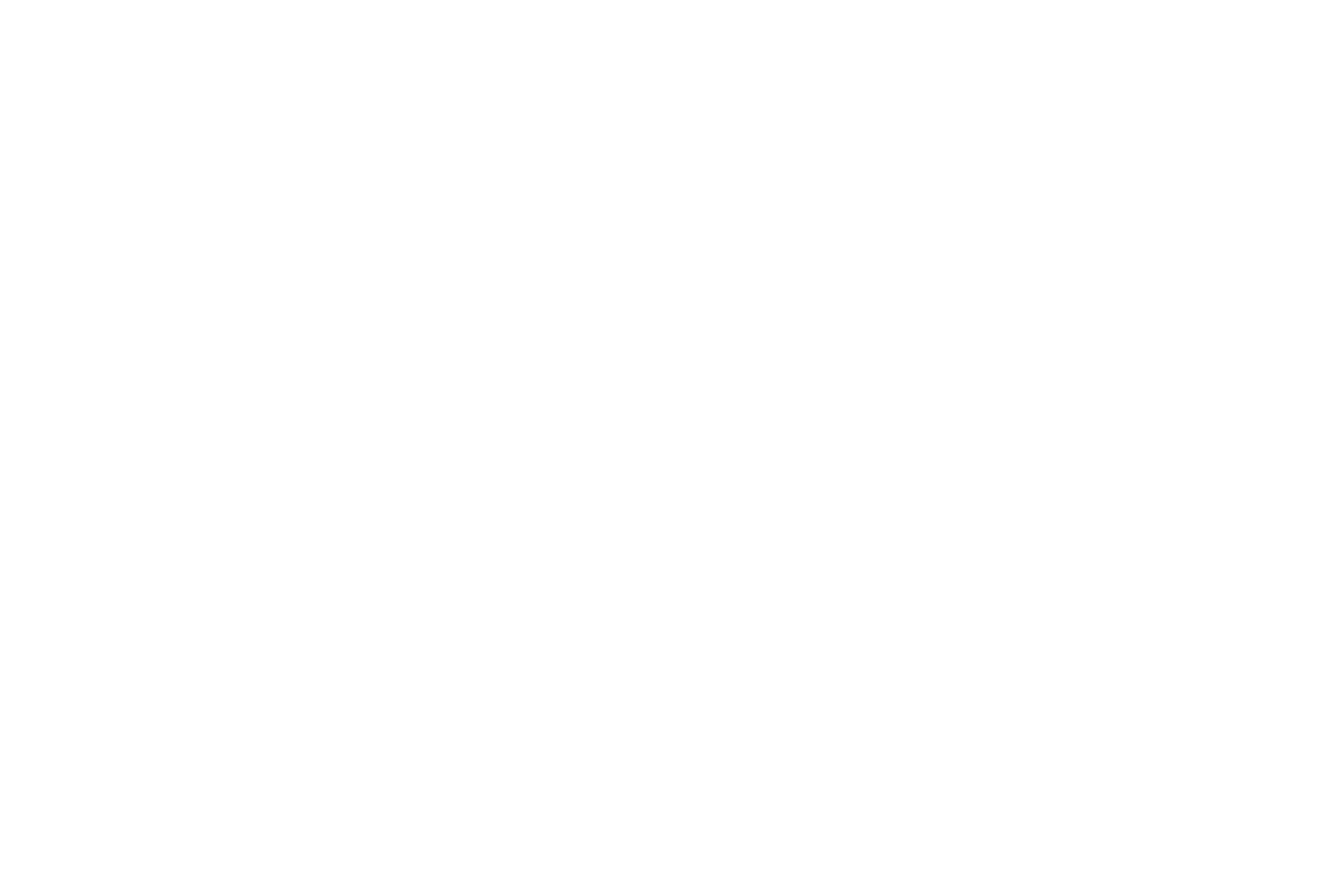
加藤さん
それも、その前にツルゲーネフの翻訳が日本ですごく流行ったり、19世紀の終わりに日本が近代的な新しい時代になった時に、もちろんアメリカとの交流も、フランスとの交流も、オランダとの交流もあったでしょうけど、音楽と文学の影響はロシアの影響が一番大きかったの。その影響の中で、みんな新しい日本の歌を作ったり、文学を作ったりしてきた。私たちの世代もロシア革命も大好きだったし、尊敬しました。その革命に至る前のアバンギャルドの時代も大好きだったし。だからロシアの文化の影響は日本の文化にすごく大きな影響を与えてきた。そういうのはずっと歴史の中にあったと思います。
加藤さん自身、「百万本のバラ」は自分の曲の中でも一番好きな歌だと打ち明けている。加藤さんは、ロシアの有名な女性歌手アーラ・プガチョワのレコードで、初めてこの曲を聞き、その後、プガチョワを東京に招いた。1987年、2人は一緒に東京の中心部にある日比谷公園の大きなステージでこの歌をうたった。このときから、「百万本のバラ」は日本人の心を魅了し、「日本の」歌になったのである。2000年、加藤さんは返礼訪問としてモスクワに行き、プガチョワとともに2カ国語でこの歌をうたい、大きな成功を収めた。
100年の歴史を振り返るコンサート
7月にBunkamura オーチャードホールで大きなコンサートがありました。コンサートは「時には昔の話を」と名付けられていましたが、これは宮崎駿のアニメ「紅の豚」の有名なタイトル曲にちなんだものですね。コンサートのコンセプトについてお聞かせいただけますか?
加藤さん
紅の豚、ポルコ・ロッソの時代は100年前、ちょうどソ連が誕生して、第1次世界対戦が終わって、次の戦争が始まるまでの、ヨーロッパが一番厳しい時代だったけど、それでも人はこれからもっと飛行機に乗って、いろんな意味で新しい可能性があるという、夢がある時代でしたね。この間の私のコンサートは、どんな時代にも強い愛と生きることへの希望が溢れるような、そういう音楽を続けてきたという、100年の歴史を振り返りましょうというコンサート。
加藤さん
私の歌手生活56年の中で一番大好きな曲だけを綴って100年という時間を感じながら、今から100年後も、私たちが今生きていることが語り継がれていくような未来があるか、私たちは未来に希望を与えることができているのだろうかというような意味で、このコロナで世界中が大変な時に、もう1回、素晴らしく生きた人たちのことを思い出しましょうという、そういうコンサートでした。
主人公ポルコ・ロッソ役を演じた森山周一郎さんが亡くなったという悲しいニュースも加藤さんにとって、コンサートのコンセプト作りにおいて重要な意味を持っていたのではないでしょうか?
加藤さん
森山さんが亡くなったことも今年、『時には昔の話を』の中に懐かしい男がいっぱいいますね、みんなまだ生きていますか、みんなはまだ元気で生きていますか、というような、そういう思いもこのコンサートにはありましたね。でも、森山さんは亡くなってしまいましたけど、きっとポルコ・ロッソは生き続けているだろうという気持ちです。
フラッシュモブなどについて
パンデミックが発生した頃、しばらくの間、YouTubeのチャンネルで、「巣ごもり日記」という日記のようなものをされていましたね。とても面白くて、加藤さんにはブロガーとしての素晴らしい才能がおありなんだなぁと思っていました。なぜやめられたのですか?
加藤さん
今は『土の日ライブ』という私の番組をYouTube でするようになったので、巣ごもり日記的なことは終わらせました。あと、洋服を作り変えたりすることをはじめました。私の母が洋裁をする人だったので、私は子どもの頃、いつも横で手伝っていました。
加藤さん:「『この手に抱きしめたい』という曲を去年の4月に YouTube で出して、色んな人が歌ってくれて、ロシア人も日本語で『この手にあなたを〜♪』って歌ってくれたんですよ。」
「四幕目は一番面白いので、絶対楽しみたい」
最近、加藤さんは人生をオペラに例えて、「人生の四幕目」である今が、人生で一番面白い時期だとおっしゃっています。四幕目に至るまでのこれまでの時期はどのようなものでしたか?また四幕目は加藤さんにとってどのようなものだと思いますか?
加藤さん
一幕目は人生のスタートで、何がどうなるかわからないけど走り始めるもの。二幕目、25歳以降ぐらいに子どもが生まれたり、結婚したり、とても忙しい25年があって、50歳ぐらいからは、また再びもう一回、女として、歌手として、25年ぐらいとても楽しい時間があった。日本では起承転結と言うんですけどね。起は起こす、スタート。承はそれがキープされる、続く。三幕目になるとガラッとチェンジする。50歳ぐらいから、もう一回、子育ても終わって、歌手として一番活動した25年があったと思います。海外にも行ったし、いろんな国でコンサートもしたし。
そうしたら、やっぱり四幕目というのは、どんなお芝居でもそうだけど、今まで準備した、今までやってきたことが全部、今のレストランで言えば、仕込みが終わっていつでも料理を出せますよという状態。自分の中でたくさんの音楽が生まれて、いつでも出せる、どんなプログラムでも、世界中のものが私の中に体験としてあって、この四幕目がすごく楽しいと思います。
だから、四幕目を絶対楽しみたいという気持ちで迎えた時にコロナが来たけど、私は楽しめる材料をいっぱい自分の中で準備してきた、一番大事な時間だから、歌手として今できることを無駄にしたくないなと思って、コンサートもずっと続けてやっています。
パンデミックでつらい時期を過ごされている人々に何か伝えたいメッセージはありますか?